
[番外編]東チベット一人旅 Vol.8 – 天へと還る時
中華包丁を持った男は広場を横切り、屋根のついた一角へやってきた。
両手に持った大きな中華包丁を入念に研ぎながら亡骸を物色している。
遺族関係者の表情は硬直しており、その眼差しはただただ亡骸へと注がれていた。
猿山の一角に座した僧は何やら準備が整ったようで、マイク越しに読経を始め、
張りつめた緊張感が漂う天葬台一帯を劈くその読経は、
ハゲワシを鼓舞する怪しげな呪文の様にも聞こえた。
中華包丁を持った男が忙しく動き始める。
何やら作業をしては上体を起こし、刃を研いでは再び作業に取り掛かった。
その作業は言うまでもなく亡骸の解体であろう。
手元が確認出来ない見物人席からでも容易に想像がつく。
その間10分程だっただろうか。
遺族関係者は眉間に皺を寄せつつも、尚も亡骸の方を直視している。
この状況にあって、自制心が保てていることが理解できない。
宗教や習慣が違えば、(広義で考えれば同じ仏教徒ではあるが)
ここまで割り切れるものなのか、俄かに信じがたい光景である。
その外ではハゲワシがまるで進入禁止のラインが引かれているかのように、
一線を守りながらも、カーテンが開く瞬間を押し合い圧し合いをしながら待ち構えている。
見物人席は怖いもの見たさが故なのか、見物人は落ち着かない様子で
席を移りながら広場の様子を覗き込む。
中華包丁を持った男は上体を起こした。
解体が終わったようだ。
そのまま、カーテンの方へ近づき、徐にカーテンを開けた。
その瞬間、ハゲワシが広場になだれ込んだ。
陸上を駆けてくるものもいれば、上空から急降下してくるものもいた。
その凄まじい勢いに砂埃が舞い、遺族関係者は
広場の中心から入り口付近の隅に追いやられた。
あっという間にハゲワシは一帯を占拠してしまった。
その数はもはや数得ることが出来ない。
地面が全く見えないほどの過密状態になりつつも、ハゲワシは蠢き啄んだ。
その一部始終は詳しく確認できなかった。
しかし、所謂、凄惨な状況に違いなかった。
広場の過密地帯の中で、数羽のハゲワシが大きく羽ばたきながら、
肉片らしきものを取り合っている。
それがもはやどの部位の何であるかは既に識別出来ない。
肉片を咥えたハゲワシが、過密地帯を脱し、肉片を咥え直し丸呑みした。
その肉片には白く色を変えた皮膚らしきものが付着していた。
ハゲワシの頭の毛は徐々に血に染まった。
血生臭ささはなく、人が喚くような声もしなければ、肉を切裂くような音もしない。
僧の読経はいつの間にか終わり、静寂が一帯を支配している。
全身の感覚が視覚に集中してしまったために、
聴覚や嗅覚にまで行き届かなかったから気づかなかっただけなのかもしれない。
残酷極まりない地獄絵図と言ってしまえばそうに違いない。
この光景をビデオに撮って日本に持ち帰り再生しようものなら、
激しく倫理観を問われるに違いないだろう。
しかし、この状況を冷静に直視出来たのは不思議な体験だった。
この日に綴った日記には「こみ上げる感情を言葉に言い換えることが
如何に野暮なことであるかを考えさせられた」と書いたように、
どういった言葉が的確なのか、その糸口すら分からなかった。
この旅行記を書くにあたって、日記をもとに校正、補足をしながら
文章に起こしているのだが、筆を進める度に、その時の光景を反芻している。
しかし、この場面においては未だに心情を的確に表すに相応しい語彙が浮かばないし、
そもそもそのような語彙を持ち合わせていない気すらしてしまう。
死者を葬る術として、この厳しい環境下では火葬、土葬、水葬は適わないため、
天葬を行っているだけで、尊厳を持ち死者を葬るその姿は
野蛮でもなければ、非文明的でもないように思う。
また、天葬という習慣により、人間が食物連鎖の一端を担い、
この厳しい環境下の生態系を守ってきたという見方もできるのかもしれない。
いずれにせよ、物質社会に生まれ、安穏と育ってきた自分には
チベットに住まう人々の宗教的背景やその精神性等を一朝一夕にして理解できるはずもない。
とりとめもない話になるので、ここらで止め、旅行記を進めてみようと思う。






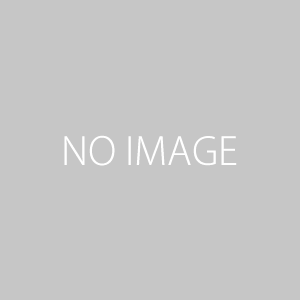
この記事へのコメントはありません。